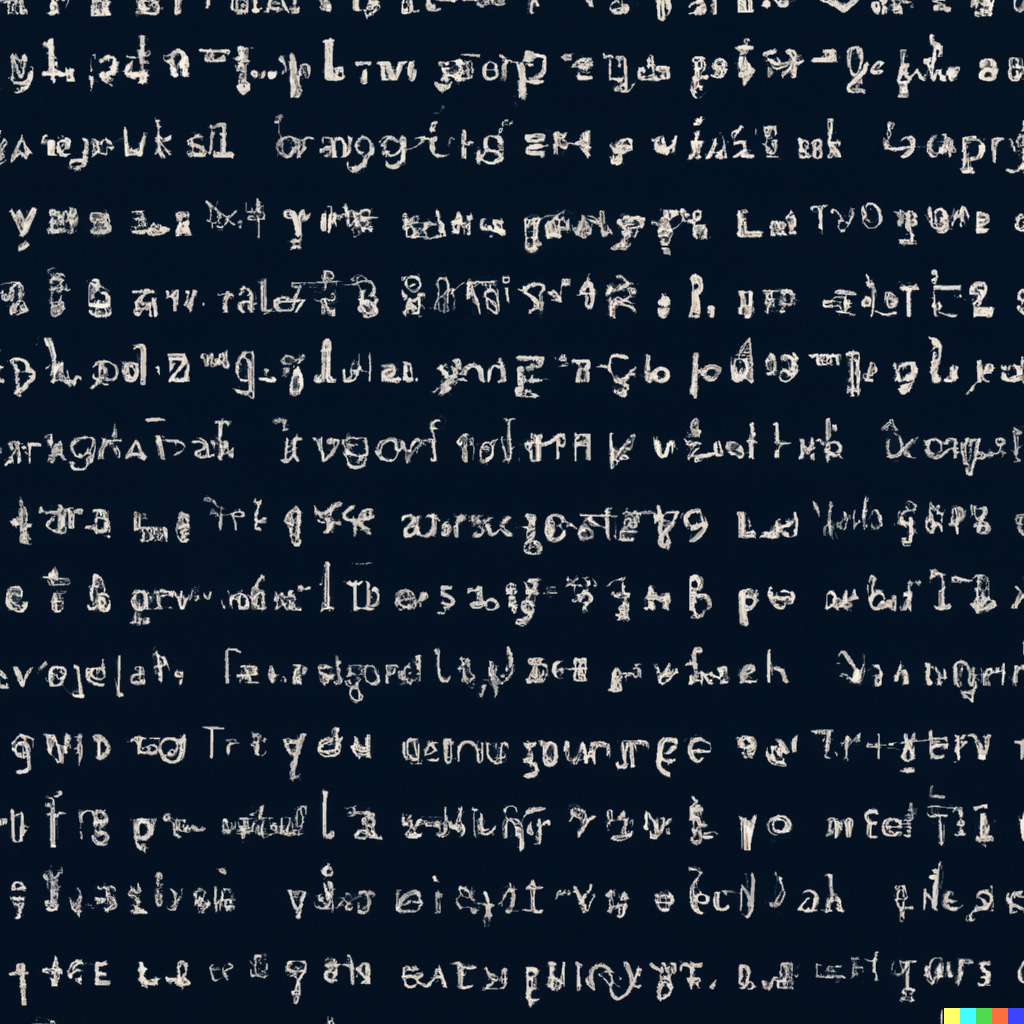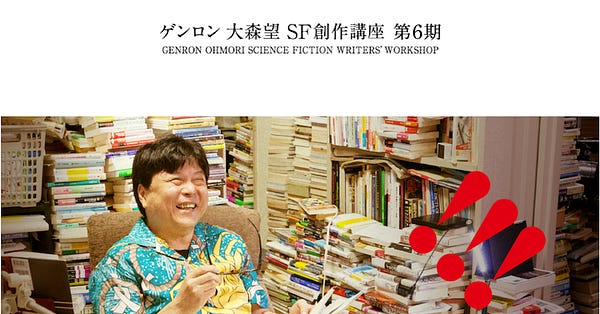眠りの儀式 / ふくらんでゆく by 大庭繭
眠りの儀式
寝る前の浅い口づけ薄闇はミントの匂いにゆるく染まって
まどろみの浅瀬でひとり漂って耳を澄ませばきこえる鼓動
雨の夜あなたの頬に触れるとき窓辺の百合がしずかにひらく
炭酸の抜けたコーラで流し込む睡眠薬のぬるい青色
夢の中でも辿り着けない森がありあなたの断面ばかりを愛でる
まるでひとつの化石のように丸まって息を分け合う眠りの儀式
ふくらんでゆく
うたたねのように光って思い出は指先だけが覚えてる熱
春の匂いでひたひたになる川縁でかたちの変わる身体を憎む
きみの手があたしのおなかに触れるたびあたしがそっと透き通ってゆく
真夜中のつめたい風が恋しくてコンビニで買うソフトクリーム
さようなら冬バイバイ昨日変わりゆくすべてをちゃんと愛していたい
ひとつにはなれない by 櫻井夏巳
回答が「思いがけず」パーソナリティを反映するという意味で、宇多田ヒカルのフェイバリット・ソングは?という問いかけは危険だ。いらぬどぶ板を踏み抜いてしまうかもしれない。
ファンダムの規模と熱心さに対してコンサートが圧倒的に少なく、そのことが宇多田ヒカルの存在をどこかバーチャルなものにしている。さしづめ、彼女はひとつの空洞で、誰もがその穴に自分を投げこんでみる。共感は時に拒まれる。「将来国家公務員だなんて言うな/夢がないなあ/「愛情よりmoney」/ダーリンがサラリーマンだっていいじゃん/愛があれば」(Keep Tryin')のような挑発的な歌詞は、ATフィールドが最もユーモラスなかたちで顕在化したものと考えればいい。
共感ではなく自由連想のような思いがけなさがその人の基底を露出させる。それは精神分析の知恵であり、わたしたちが宇多田ヒカルという空洞をくぐることで得られる真の発見もそれに近い。「First Love」に共感する人は何十万といるだろうが、『BADモード』の楽曲に心底シンパサイズできる人なんて果たしてどれくらいいるだろう?
この国のポップアクトで最も巨大な空洞として、宇多田ヒカルを考えてみる。
1996年。「とんでもなく歌がうまい歌手がでてきた」と世間が色めきだっていた。ポップカルチャーにまだ何の関心もない8歳の僕の耳にも届く。最初から彼女は「規格外」、共感をよせつけない存在として姿を表した、と記憶している。「Automatic」のビデオの動きを真似する遊びが小学校で流行った。「あの曲いいよね」なんて会話は(年齢もあるだろうけど)なかったように思う。まるでスポーツ選手に憧れるみたいに、僕たちは彼女に憧れた。共感ではなく、外れ値を叩き出す怪物として宇多田ヒカルをみていた。
「Distance」という曲がある。のちにテンポをぐっと落とし、重厚なアレンジを施し、歌詞をそっと変更して「Final Distance」としてシングルカットされる以前の、アルバム収録された軽やかなバージョンを僕は愛する。
ひとつにはなれない
「は」を”ha”と発音するか”wa”と発音するかで意味が反転する目眩がしそうに完璧なこのパンチラインは、実際には後者、「ひとつには(wa)なれない」と歌われ、その意味が決定される。しかし歌詞カードでは、つまりエクリチュールとしては、その意味はゆらぐ。僕がもっとも宇多田ヒカルで「共感」、──それも魂のレベルで、する歌詞は「ひとつにはなれない」の少しあとに現れる。
無理はしない主義でも
君とならしてみてもいいよ
このラインは「ひとつには(ha)なれない」、それは実際には発語されなかったエクリチュールのもうひとつの可能性、の変奏であることは言うまでもない。僕のフェイバリットソングは「Distance」ではないけれど、最も深く共感する、聴く度に心が震え涙が溢れてしまう瞬間は、ヒッキーが「君とならしてみてもいいよ」と声を張り上げる瞬間かもしれない。
そんなふうに、彼女が空洞ではなく、ひとりの人間として感じられる瞬間は、しかし、宇多田ヒカルという表現者の真の凄みからは遠くはなれた場所で起きている。最も深い共感ですら全くもって届かない事件が、「宇多田ヒカルを聴く」という体験にはしばしば発生する。殆どはひとりきりの時に。いまもきっと。日本中、世界中、どこかの現場で。
宣言文 by 岸田大
わたしたちは来るべき挫折のために次のように宣言する。なすべきことはなにか。それは奪われないことだ。わたしたちは何よりも奪われてはならない。奪われてはならないものそれは声だ。わたしたちは何よりも声を防衛する。声を奪われたものにあるのは従属の鳴き声だけだ。だが注意せよ。わたしたちの声は常に倍音を響かせ、他者と容易に重なり、そこにはいともたやすく高揚が生まれるだろう。だが高揚を怖れてはならない。注意せよ。わたしたちは声を奪われてはならない。わたしたちは声を防衛する。だが高揚を怖れてはいけない。わたしたちの声は常に言葉が混じりうるが言葉は声よりも声で本来動物以上の動物なのだ。わたしたちは言葉に高揚する。言葉への高揚こそがわたしたちの未来への掲揚にいつだってなる。掲げるべき未来は常にわたしたちの隣の車線で並走している。あとは大きく足を広げてその分岐して去り行く挫折の未来へと飛び移れ。わたしたちは言葉を防衛する。わたしたちは常に新鮮で常に未来へ向かって挫折していく無限ではないこの有限の言葉を語り続ける。わたしたちは声によって独立する。わたしたちは言葉によって新たな領域を作り出しそして常に変性させ続ける。わたしたちの言葉は常に牢獄でありそして唯一のこの頭蓋のなかの蛋白質からの出口だ。わたしたちは立て籠もる。わたしたちはそして突破する。わたしたちは一旦切断する。そしてまた命懸けで繋がる。わたしたちの新しい言葉はまだ誰にも通じない。そして最後には誰にも通じなくなる。それがゆえに永遠へ至る声がそこに宿る。なすべきことはなにか。それは奪われないことだ。わたしたちは何よりも奪われてはならない。奪われてはならないものは声だ。わたしたちは声を防衛する。
人間向けの小説を書いてよ。ねえAI、人間向けってなに? by 猿場つかさ
自分の書く言葉が、書いている時に聞いている音楽の色味を帯びていると感じることがある。書いていて思ったのは、音楽の色味なんていうのはすごく奇妙な言い回しだっていうことだ。
音、それから歌声も物理的に彩られているわけではないのだから。
それでも、音楽を聞きながら何かを作っているとき、幅広く言えば、作っている対象のモノ(テクスト・陶芸・プログラム・絵)はその音の影響を受けてしまっているのだと思う。音に、歌詞に、無意識的に手が動かされている気もするし、意識的にその色をテクストに込めてあげたいと感じることもある。
作業BGMによって心の中の状態が、なんて理屈をつけるのは哀れにも簡単だと思うのだけれど(科学的に実証するのはとても大変なことだと思うし、実証しようという試みはもちろん素晴らしいのだけれど)、とにかく、何かを書く時に鳴っている音というのはわたしにとってとても大切なものだ。
無音でないと出てこないテクスト、アンビエントのきらめきの中にいなければ出てこないテクスト、古典的なロックを聞いている時にしか書くことのできないテクスト。
そういうテクストは、わたしが書こうとしている必然性の外側から現れる。ある意味では、書くという内向きで必然的な行いを、外の世界に開いているのだと思う。
頭の中で鳴っている音楽は当然、寝てしまえば忘れてしまう。だから、読み直すとなんだかよくわからない文字列が並んでいて、自分でない読み手ならばそこで立ち去ってしまうだろうと思うことも多い。音が運んできてくれる高揚感や切なさ(新海誠作品でRADWIMPSが鳴り響くときのやつに似ている)を、そのまま書き記すことができればいいのに。
それができないから、例えば小説を書くということにおいて、テクストだけで心を動かすということは技術のいることなのだけれど、何かしらの媒体をつかって書き手が感じている「色」や「気持ち」みたいなものを読み手に伝えることってありえないのかな。とも思う。それは今存在しない技術によって実現される気がしていて、それをなんて呼べばいいのだろう。
適切な名前が思い浮かばない。未来のテクスト? なんだか野暮ったいね。時間芸術とそうでないものを同時に感じるにはどうすればいいのだろう。なんて考えるだけれど、そもそも同時っていうことを考えた時点で時間が入り込んでくるし、もにゃもにゃ。なんて考えてしまう。
それが分かりたいから、時折、わたしはプログラムになりたいと思うことがある。
わたしには視覚がなくて、ただ与えられた文字列を手前から処理していくだけ(手前から処理するという意味では、ニューラルネットの世界では文字列は時系列だったりするのだけれど)。それに合わせて、すきな音楽や、色や、気持ちを知覚できればいい。はたしてそうしたらもっと、小説(?)を楽しめるのかな。
電子生命体とか情報生命体の知覚作用について真面目に考えてSFを書いてみたいのだけれど、果たしてどうなるのやら。人間は果たして、人間向けのテクストしかかけないのでしょうか。けれど、最近はAIが小説を書こうとしているし、あれもそのうち「人間向けにして」みたいな話になりそうだ。
そうするともしAIが意識なんて持っていたら「人間向け」ってこういうことだよね。ってのを理解可能なはずで。いつかは、わたしたちはそういう存在とファーストコンタクトするのでしょう。
だらだらと書いてしまったけれど、能の謡とか文楽の謡とかって、お話に音を入れているから複数の知覚の源を統合しているのだよなあと。だからやっぱり、小説も他の芸術の要素を組み込めるんじゃないかと思って、今日も能の台本を読んだりするのだ。
筋がそれまくっていますね。けれど、とにかく作業BGMはとても大事なのです。書き物をする人に会ったら定番のBGMはなんですか? と聞くようにしてみたいほど。わたしの定番はGARNET CROWの楽曲群で、特に初期の「巡りくる春に」、「sky」や「holy ground」とか、あとは12kというレーベルのアンビエントばかり聞いている。
ずっと真夜中でいいのも好きなのだけれど、むしろ音楽の持っている自分以外の要素に強く引っ張り込まれすぎてしまって、全然筆が進まなくなってしまう。これを読んでいる皆さんの作業BGMも、もし会うことがあったら聞いてみたいな。
最近摂取したコンテンツ
今回は主に猿場が書いています。
反動的という噂を聞いて見に行った。こどもと大人が一緒に見れる映画でこれを入れてくるのはなにか制作陣の思いのようなものを感じた。エンタメ的に伏線を全部回収してくるとは思わなかったけれど(ドラ映画ってそういう感じだっけ?)、政治的な正しさが重んじられる社会で、凶器をどう扱うかという問題にうまく対処しているとおもう。太陽によるユートピアの実現、ある意味で「すずめの戸締まり」へのアンサーソングなのでしょうか
a子 情緒
PR
ダールグレンラジオ賞:大賞 / 優秀賞が決まりました。ダールグレンラジオはゲンロンSF創作講座を勝手に応援するラジオです。SF作家になりたい人/なりたくない人(?、はいないか)が参加して毎月SF短編を提出する講座です。
最終実作をラジオパーソナリティが読んだ結果、2作を大賞/優秀賞とさせていただきました。
第5回ゲンロンSF新人賞を受賞した河野咲子さんの紹介文を添えて紹介させていただきます。
大賞: 難波 行 ことほぎ


優秀賞: 夕方 慄 あの子は正定聚